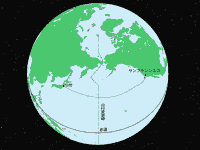-- これは実話です --
1・嵐 2・好天 3・近接
1・嵐

出発の翌朝、まわりには海原しかなかった。
夏の末に海水浴場に打ち寄せる、台風の荒波。轟音をたてて巻き崩れる高波。いや、それ以上の大波が次々と、小さなヨット[青海](あおみ)を襲っていた。
白帆に風を受けて、傾きながら走るヨット。波が横腹を打つたびに、さらに傾いて横倒しに近くなる。大波は数メートルも船体を持ち上げて、次の瞬間、一気に船底の下を通り過ぎ、ヨットは波の頂上から谷間に激しく落下する。狭い船室では大地震がきたように、食器、雑誌、ハーモニカ、ナイフや玉ネギまでが宙を舞い、次々と顔に飛んでくる。近くに台風でもあるのだろうか。
頭はズキズキ、目はグルグル、強い吐き気も込み上げて、胃が本当に苦しく、胃の形を感じるほど苦しくて、船室のベッドに寝たきりのまま、一日、さらに一日と過ぎていく。だが、自作のウインドベーン装置が自動的に船尾で舵をとり、[青海]はたくましく、波にも負けずに走っている。ヨットはこんなに強いのに、ぼくはあまりに弱すぎる。
船酔い止めの薬を飲もうか。いや、飲み始めたら習慣になって、いくらあっても足りないだろう。日本で陸の近くを走っていたとき、ぼくは船酔いに強いと皆に評判だったのに。これほど波が高く、これほど陸と違う世界だったとは、想像さえもしなかった。
揺れ続ける体を支えようと、全身の筋肉が無意識に動くのか、ヨットの上ではベッドに寝たままの姿勢でも、体力の消耗が激しい。そのうえ嵐が始まってから二日間、何も食べていないのだ。強い疲労と空腹で、体力の限界を感じていた。腕時計を見たくても、手を持ち上げる気力もない。
体が動くうちに、何かを口に入れないと、やがて衰弱死するだろう。力をふりしぼるようにベッドを出ると、タタミ一枚ほどの小さな床に座り、桃の缶詰を開けた。胃が受けつけないのは知っている。だが、数メートルも上下する床の動きと合わせるように、スプーンをタイミングよく口に運ぶと、驚くほどうまい。あっという間に一缶分を食べきった。缶詰に感激したのは、生まれて初めてかもしれない。
最初の目的地、米国のサンフランシスコまでは、八千キロを超す長旅だ。赤道一周の五分の一にも相当する。なのに出発直後から、ぼくはもう弱音を吐いている。
苦しみに負けない精神力と体力を、自分は備えているだろうか。広い太平洋を本当に自力で横断できるのか。海から陸に生きて帰るのに必要な、天から与えられた資格があるだろうか。激しく揺れるベッドに入り、船酔いで痛む頭をフトンに埋めていた。
すると上空を前線が通過したのか、急に風向きが変化して、ヨットはコースを外れてきた。帆とウインドベーンを調整するために、船室のハッチを開けて顔を出す。と、すぐ横の海面が、本物の丘のように高く盛り上がり、頭上に真っ白く泡立って崩れてきた。「危ない!」叫んでハッチを閉める。と同時に波の直撃を受けたヨットは、ほとんど真横に倒された。ぼくの体は船室内で、下に回った横壁に落ちて打ち当たる。が、次の瞬間、船底についた八百八十キロの鋳鉄製バラストが、バランス作用を発揮して、ヨットは自動的に立ち上がる。だが、あまりにも急に起きたから、体は船室を横切るように飛ばされて、反対側の壁に激しく衝突した。
頭と胸を強打して、しばらく呼吸できなかった。起き上がって船室内を見回すと、ハッチを閉める直前に入った海水で、フトンも食糧もずぶ濡れだ。「油断していた!」大波の襲う瞬間に見上げた、波頭の崩れ散る鮮烈な白が、爆発のまぶしい閃光を目撃したように、脳裏に刻みついていた。
二日後、嵐が勢いを弱めても、頭の痛みは続き、胸にはアザができていた。肋骨にヒビでも入ったのか、深呼吸すると胸が痛く、咳のたびに激痛が響く。精神状態も異常に高ぶり、夜中に理由なく目覚めてしまう。ハッチから頭を出して外を見回すと、黒い海面にチラチラと立っては消える、箸かマストのような、奇妙な光の棒。水平線の少し上には、不気味な赤い三日月が出ている。
「お月さん、お願いだよう、ぼくをなんとか助けてくれよう」
2・好天

つらい嵐が過ぎ去ると、輝く太陽と軽風の日々が訪れ、数日後には再び嵐が始まり、また終わる。天気は周期的に変化した。サンフランシスコに向かうヨット[青海]が、メルカトル海図上でほぼ一直線に走った、太平洋北緯三十八度ラインの夏だった。
晴天の陽射しの中、白帆をまぶしい優美な曲面に膨らませ、光り輝く海を自在に駆けるのは、心地よい波切り音と爽快な風、広大な海原を突っ走る充実感の世界だった。船首に砕ける小波は一瞬に太陽を反射して、まるでガラス細工の波飛沫。それにしても海が青い。白い布をひたせば、ブルーのハンカチができそうなほど。
嵐のときは船酔いで倒れていても、晴天がくると不思議に元気が出る。今までが仮病のように、ベッドから跳ね起きて生活する。毎朝六時半に目覚まし時計が鳴ると、六分儀で太陽高度を測り、三角定規や計算表を使って海図に現在位置を作図する。次にチャーハンなどを炒めて、朝昼兼用の食事をとった後、濡れた衣類を手すりに干したり、船体各部を点検したり、故障が見つかれば修理もする。海水で湿った数十枚の米ドル札を、海苔を焼くようにコンロで乾かす日もあった。やがて夕飯を終えて日が暮れると、室内灯で日誌をつけ、何冊も積んだヨット航海記を読んで寝る。でも、真夜中にコンパスで針路を確認したり、突然の風雨に驚いて飛び起きたり、嵐がくれば帆を小さなストームジブに張り替える。草原で天敵に脅えて暮らす野生動物のように、ゆっくりと熟睡はできなかった。
海の上で一人きりの、長いようで短いような、陸とは別世界での一か月がたったとき、ヨット[青海]は四千キロ以上を走りきり、北太平洋横断航海は、すでに半ばを過ぎていた。
百二十リットル積んだ飲料水は、八十リットルも残っている。一日平均、わずか一・三リットルの消費量。これで飯を炊いてミソ汁も作る。もちろん食後は茶を飲んで歯も磨く。でも、米をとぐのは海水だ。一日一回、燃料も水も節約できる圧力鍋で、ぼくは三合の米を炊いていた。海の空気と一緒に食べる熱々の炊きたては、ウメボシ一個でドンブリを空けるほど感動的な味がした。
ひとりぼっちが続く北太平洋の真ん中で、風の静かな晩はデッキに数時間も寝転んで、飽きずに夜空を眺めていた。人の密集する町を遠く離れた本物の夜空には、今にもザァーと音をたてて降り落ちそうなほど、大粒の星々が光っている。ヨットは闇の中に浮き上がり、銀河の海を旅しているようだ。まぶしい星空をバックに、帆が黒い影絵となりながら。
満月の夜は、青白い光が大気中に充満し、水平線が昼間のように見渡せた。しんしんと降りそそぐ音が聞こえそうな月明かりの下、黒光りする巨大な生き物のように、力強くうねる海原。ヨットは心地よい水切り音を小川のようにたてて、幻想的な海を駆けていく。
それにしても、大洋を照らす月は明るすぎた。窓から射す強い光に驚いて、ぼくは何度も夜中に飛び起きた。船が来てサーチライトで照らしていると、本当に勘違いしたからだ。
3.近接

ゴールデンゲートブリッジと砂漠の山々は目前だ。
陸の常識が通用しない海の上で、八週間を暮らしたころ、船室の時計は六時間も進められ、北太平洋東西八千キロ余りの海原を、ほとんど渡り終えていた。
進行方向から近づくカモメのような二羽の鳥。青空に純白の腹を見せながら、マストの上を二度旋回し、アメリカの方角に飛び去ると、また引き返して同じ動作を繰り返す。船を先導するという、パイロット・バードだろうか。日本近海を離れてから、鳥をほとんど見ていないのに、再び鳥に会うのは、陸が近い知らせに違いない。ラジオからは英語の歌やニュースも聞こえている。ゴールのサンフランシスコは目前だ。
なのに、翌日から嵐が始まって、鍋もヤカンもコンロに置けないほど揺れ始め、ぼくの体は船室内を何度も飛ばされた。夕暮れ過ぎ、その日最初の食事を缶詰ミカンとビスケットで済ませると、またしても船酔いで、ベッドの上に横たわる。波の頂上から谷底に、小さなヨットは投げ落とされ、船底を通った着水の衝撃が、ぼくの背骨を痛いほどに強打する。船室の外では暗闇に、人を脅迫するような風の声。
アメリカ大陸まで、推定百キロ。未知の海流に押されていれば、夜明けまでに衝突の危険がある。
「外に出て、灯台の明かりを探せ」が、できない。空腹でもなく、体力も消耗していないのに、金縛りの呪いにかかったように、体が全く動かない。ベッドに寝たまま恐怖で少しも動けない。船室を出たとき、波に打たれて落水しても、助けてくれる人は誰もいないのだ。
ところが真夜中過ぎ、反射的に跳ね起きる自分の姿を感じていた。急いでハッチを開くと、すぐ目の前に、白波の砕ける島々が見える。サンフランシスコ沖のファーラン諸島に違いない。コースを変えないと衝突する。でも不思議だ。一つ一つの島は直径二メートルもない。誰かが粘土の模型を作って並べたようだ。しかも、真っ暗闇のはずなのに、島々は奇妙なほど鮮明だ。おかしい。何か、きっと何か狂っている。が、次の瞬間、ぼくは島々を避けることを全く忘れ、カメラを海に向けていた。フラッシュの光が届くほど島々は間近い。急いでコースを変えないと数十秒で衝突する。いや、もう手遅れだ。岩に砕ける波飛沫が次々と顔を打っている。
――ふと目を開くと、体はベッドの上を飛び回り、本や食器が宙を舞い、窓の外の暗闇では、風が悲鳴をあげている。このまま前進を続ければ、夢は正夢になるだろう。
なのに、恐怖心と船酔いで、起きて見張りをする勇気も元気も気力もない。
「小型ヨットのスピードなんて、のろい自転車と同じだ。陸は遠いに決まっている、どうせ大丈夫だ寝てしまえ」
こんな言い訳をするようでは、海を無事に渡る資格も、海から大切なことを教わる資格もない。そんな心構えでは、仮に太平洋を横断できても、次に向かうホーン岬の嵐で命を落とす。泣きたいほどに悔しかった。
朝がきたとき、嵐は夢のように去って、空は原色の真っ青だ。水平線に乱反射する朝日で染まった低い空には、うっすらと山の形が浮き出ている。目指すアメリカ大陸、二か月ぶりの陸地だった。
波の消えた大平原のような海面を、帆に微風を受けて進み続けると、夕方までに陸の二十キロ手前に達していた。やがて夜と同時に凪がきて、黒光りする油のような水面に、船体はピタリと止まって動かない。彼方には、洋上で慣れ親しんだ月や星とは違う、全く異質で異様な明かりが、車のライトの動き回るサンフランシスコの町の灯が、夜空をこうこうと白く染めている。
あたりは下水のように臭い。子供のころドブ川で拾ったタニシ貝を思い出す。日本の海も同じだろうか。町という人の群れを遠く離れ、澄んだ海水で毎日のように米をとぎ、頭上から純白の波を何度も浴びながら、海とともに生活した者だけが、気づく悪臭かもしれない。
沿岸を行き交う船との衝突を恐れ、見張りを徹夜で続けていた。二か月間の不便で苦しい海の暮らしも、いよいよ明日で終わり、揺れない陸地で生活できる。夜冷えのデッキで熱い紅茶を飲みながら、ぼくは複雑な気持ちになっていた。
それはゴールを目前にした喜びや感動ではない。未知の国アメリカに対する不安が、心を占領していたのだ。生活費はどうするのか、アルバイトは見つかるか、言葉は通じるだろうか。次の目標、嵐のホーン岬を目指す準備はできるのか。
翌日、アメリカ西部時間の正午、全長二・八キロの大吊り橋、赤さび色に塗られたゴールデン・ゲート橋の下を通過して、ヨット[青海]は秋のサンフランシスコに到着した。
アメリカ、生まれて初めての外国だ。
***大平洋横断については、BlueWaterStory04もあわせてご覧ください。